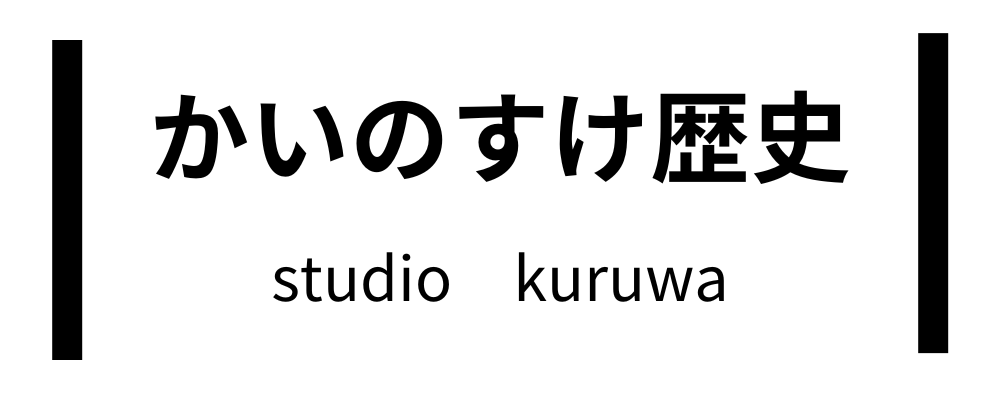静岡県大井川のあたりにあるお城というと、どこを思い浮かべるでしょうか。
城好き・歴史好きな方なら丸馬出で有名な諏訪原城とか、武田と徳川が奪い合った高天神城などが出てくると思います。二つとも、全国レベルで有名な城ですからね!
ところがこのあたりでお城といって真っ先に出てくるのが小山城(こやまじょう)。吉田町にあるなかなか魅力ある城です。
なんといっても小山城には天守がある。
静岡県で天守のある城というと他に浜松・掛川城くらい。やはり誰が見ても城だ!とわかるその存在感は、無視することはできないのでしょう。
しかも小山城はなかなか良い場所に建っている。小高い丘の上にありその姿はとてもカッコいい。
口コミを見てみると「自然豊かな公園で桜の名所」「天守閣からの眺めは最高」などなかなか好評のよう。皆に愛されている城です。
ですが城好き・歴史好き目線で見ると、小山城の最大の見どころというか注目ポイントは天守や眺めや桜ではなくて、もっと別のもの・・。
小山城のスゴイところ!それは三重の三日月堀です。
「三日月堀がある」というだけでテンションはあがりますし、それが「三重構造になっている」なんて聞いたら「どんな手を使っても見てみたい」と思うレベルの特別な遺構です。
小山城を奪い合った武田信玄と徳川家康
小山城は戦国時代の城。
駿河国と遠江国の境である大井川に近い丘の上にあります。
いつ築かれたのかは不明ですが、古くから「山崎の砦」というものがあったようです。
桶狭間の戦いの後、今川領に攻め込んだ武田信玄と徳川家康。このとき大井川を境に信玄が駿河、家康が遠江を領有するという約束をしたようです。ところが信玄はこの約束を破って遠江に侵攻(1568年(永禄11年)12月)、山崎の砦を攻め落とします。(この約束は徳川方の史料によるもので、信玄が不誠実な人間であったかどうか真相は不明です)。
これに対し家康は反撃し砦を奪い返すのですが(1570年(元亀元年)4月)、翌年、信玄は再び砦を攻撃(1571年(元亀2年)2月)。
このときは2万5,000人の大軍を率いてきたということで、最終的に山崎の砦は信玄のものとなります。
信玄は築城の名人と呼ばれる家臣馬場美濃守に砦の大改修を命じます。
「二度と徳川に奪われてはならない。」という強い想いがあったのでしょうか。このときに複数の曲輪や三重の三日月堀が造られたと考えられています。
そして山崎の砦は「小山城」と改名され、武田の城として使われることになります。
どうして信玄も家康も山崎の砦改小山城を欲しがったのでしょうか。それは、この城がとても重要な位置にあったからです。
小山城は牧ノ原台地の先端にあり、目の前には大井川が流れています。武田が遠江に攻め込むときの海沿いの攻撃ルートにあり、重要な前線基地となる場所でした。
さらに当時は城の周囲を川が囲んでおり、防御に優れた地形でもありました。
一方徳川にとってはここに武田軍がいることは脅威。できれば追い払いたいもの。
小山城は両者にとって、無視できない城だったのです。
小山城見学は能満寺内部の階段を登っていきます

小山城があるのは静岡県榛原郡吉田町。JR藤枝駅や島田駅からバスがでています。(片岡北吉田特別支援学校で下車、徒歩5分)
車なら東名高速道路吉田ICから10分ほど。能満寺(のうまんじ)の南にある吉田町営駐車場(無料)を利用することができます。
駐車場からは既に小山城の天守が見えています。なかなか高い場所にありますね。
ここから歩いて城の跡に行こうと思うのですが、こんなときどうしても山側から見てみたいと思いませんか?
小山城は周りを川に囲まれていたので、攻め込むには西側の台地が続いている方向から・・ということになります。なので、こちらからアクセスすれば「攻撃側」の視点で見学できるのではないか?と私は思うのです。
ということでしばらく横の坂道を登っていきます。ちょっとどこを歩いてよいのかわからない道路なのですが、車があまり来ないので大丈夫だと思います。
ところがこの判断、大失敗でした。
実はこちら側からだと小山城に行くことができないのです。いや、もしかすると行けるのかもしれませんが、どなたかのお宅を通らなければならないよう。向こうの森が小山城なのですけどね。
ということで元の道を引き返します。まあ、地形を見ることができたのでよしとしましょう。
小山城の入口は横断歩道を渡ったお寺の中にありました。よく見ると看板があったのですが、見落としていたようです。というか看板倒れていましたよね?
能満寺(のうまんじ)は鎌倉時代(弘長2年 (1262))からここにあるお寺 。
ちょうど山の麓にあるので、小山城の一部であったのかもしれません。城の保有者である武田や徳川から庇護を受けていたようです。
裏手に回ると「歩いて登っていけるよ!」という気軽な看板が。
展望台とあるのでここから小山城に行けるのでしょうか。そしてその先に出現するのが急階段です。
「これはやばいな・・」と思ったのですが現在は立ち入り禁止。横の緩めの階段を登っていきます。
登った先にはお堂のようなものがあります。ここは一段低い場所にあった曲輪の跡のようですね。
裏手には土塁の跡のようなものがあるのを見逃しませんでしたよ。
そしてその先を進むと広い空間に。ここが小山城の中心部です。
何といっても目立つのが天守。
三重の望楼型で一階部分は下見板張り。角には石落としが見えますね。右側に付櫓があります。正面に「唐破風」(からはふ)。最上階は柱や梁がみえる「真壁造り」(しんかべづくり)で廻縁(まわりえん)と高欄(こうらん)が巡っています。
といってもこれは模擬天守です。1987年(昭和62年)に建てられてたもので、正式名称は「展望台小山城」です。
デザインは犬山城を模したものということで、それは伝わってきます。この現代の天守があることによって小山城の存在が皆さんに知られているわけです。ありがたいです。
天守はたいてい城の中心となる本丸とか本曲輪などと呼ばれる場所にあります。ですが「展望台小山城」は二の曲輪という中心部分ではない場所に建っています。
では小山城の本曲輪はどこにあったのかというといちばん東の部分、まさに公園!という場所です。
これだけ広いので、小山城には兵や物資を置くことができ「兵站基地」の役割があったのでしょうか。
昔は周囲に土塁が巡っていたと言われ、現在は南側にその痕跡が見えます。
小山城の構造を模型で見学

戦国時代の小山城の姿をみていただきましょう。これが小山城です。
どよ~んとした土の塊。天守も桜もありません。現在と大分イメージが違うと思いますが、武田信玄が改修させた小山城はこのような様子であったと考えられています。
川にかこまれた岬のような台地。いちばん先端にあるのが本曲輪です。まわりは高さ約20メートルもある崖になっていて、こちらから攻め込むのは絶対無理ですね。
本曲輪の外には堀があり、虎口の前面に丸馬出が設けられていました。
その隣に現在天守(展望台)が建っており、この部分が二の曲輪です。
能満寺があるのはその下で、駐車場からこの崖をのぼってきたのですね。
二の曲輪の外側には何重にも堀が設けられていました。そして正面にあったのが三重の三日月堀です。
なんとなく小山城の造りがわかってきました。
復元された丸馬出

本曲輪入口の馬出が復元されています。
展望台小山城の正面にある丸い堀。これが馬出の外側にある三日月堀で、土塁に囲まれた内部は本曲輪の入口を守る陣地です。
ここを通過してから橋を渡ってやっと中に入れる構造だったのですね。
「ネットが被せてあって雰囲気がイマイチ」なんて口コミがありましたが、おそらく崩れ防止のために必要なのでしょう。現代も戦国時代も城の維持というのはいろいろ大変だったのだと思います。
展望台小山城から城の様子がよくわかる

展望台小山城に入ってみましょう。入口に武田の菱があるのをチェックしてしまいました。
内部は資料館で入館料は200円です。先ほど紹介した戦国時代の小山城模型はここの一階に展示されています。
昔の学校のような階段を登っていくと展望台に続きます。
最上階にやってきました。見晴らしはいいですね。南方向は太平洋が見えます。見渡す限り平地が広がり、この場所だけが高いことがよくわかります。
東側は木があって眺望はイマイチ。大井川が流れているのを見たかったな。
この展望台が凄いのは小山城全体を眺めることができること。二の曲輪に建てられているという場所っぷりが良いのでしょうか。
右が本曲輪。赤い橋の部分が馬出です。その隣が二の曲輪。そしてあの森の部分が三重の三日月堀です。
小山城の弱点は西側。こちらは台地続きになっていて高低差がありません。その部分を守るために手の込んだ防御施設を設けたのですね。
台地からの攻撃に備えた小山城の防御施設

それでは、小山城の西側の防御を見てみましょう。
一度北側に降りて登っていきます。右手が先ほど私が行こうとして通れなかった方向で、小山城はこちらからしか攻撃できない造りになっていました。
登った先に門の柱を立てる石があります。もちろんこれは現代のものです。
ただこのあたりが昔から城の入口だったようで、両側には巨大な堀がありました。
そして小山城最大の見学ポイント、三重の三日月堀です。
なぜかこの部分だけが林になっていて暗い雰囲気なのですが、遺構を保存するためなのでしょうか。
三日月堀は西側を除く三方を回れるようになっているので、位置を変えて眺めてみるととても面白いです。特に南側からはその構造がよくわかります。
本当にカーブした三日月の堀が三本あり、一番奥は高い土塁となっています。これを乗り越えて攻め込みなさいというのはとても無理な話ですね。
ちょっと困るのはどの程度まで入ってよいのか不明なこと。「立ち入り禁止」と書いてあるわけでもなく、一方で自由に歩いたら「遺構が荒れる」なんて怒られそう。
結局近づいただけで中には入らなかったのですが、私が子供だったら堀の中まで降りているはずです。
さてここで三重三日月堀の凄さについて紹介します。
三日月堀とは半円形の堀で、丸馬出(うまだし)の外側につけられることがほとんどです。
馬出は虎口の前に設けられた陣地のようなもので、武田氏や徳川氏は丸い形をした馬出を多く築いています。
この堀を何重にするかはさまざまなのですが、たいていは一本です。
大きさもさまざまなので数が多ければ良いとは言えないでしょう。

日本一の丸馬出と言われる諏訪原城には、巨大な三日月堀が一本使われています。

二重の三日月堀というと有名なのは長野県にある伊那大島城。ここも武田の城です。
城の正面入口にある馬出の堀底には土塁があり、二重構造になっています。
攻撃兵はここに飛び込んだら一度土塁を乗り越えて再び堀に入り馬出にとりつかなければなりません。
この間の土塁を乗り越えるというのがとても大変ですね。

そして三重というのはほとんど聞いたことがありません。おそらく小山城だけでしょう。
堀は内側がいちばん狭く幅7メートル、外にいくにつれ9メートル、10メートルと広くなっています。
なぜ小山城は三重になっているのかは私にはわかりません。
巨大な三日月堀を一本掘るのと細かく三重にするのでは手間のかかりようが違うのかもしれません。もしかすると地面が固く掘りにくかったのでしょうか。
三日月堀の南側にも堀の跡があります。
小山城の西側の台地の幅は約150メートルあり、中央に三日月堀、南北に掘を設けることで入口を二箇所に絞り、固く守る構造だったのでしょう。
北側の脇道を入ると城の遺構?なんて思うものがあったのですが、どうやら崩落があってかなり形が変わっているようです。
ちなみにこの三日月堀の見学中、誰も周囲にいなかったことを報告します。もっとたくさんの人でごちゃごちゃしていても良いように思うのですが・・。
武田信玄が築かせた小山城。
その後も武田の城として使われましたが長篠の戦いの後遠江の武田軍は劣勢に。
周囲の城が徳川軍によって落とされる中、小山城は周囲の城と共同戦線を張って抵抗。堅牢だったのか、武田滅亡直前まで小山城は持ちこたえます。
三重の三日月堀も城を守るのに役立ったのでしょう。
小山城いかがでしたでしょうか。模擬天守と公園そして桜もよいですが、三重の三日月堀、是非ご覧になってください。