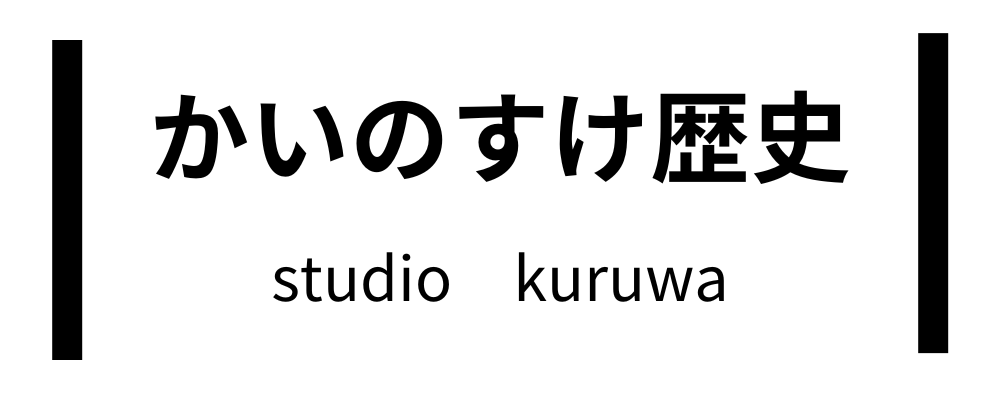武将マニアのヒーロー「小田氏治」
皆さん常陸の国の戦国大名、小田氏治公をご存じでしょうか?教科書にはきっと出てこないでしょうが、実は城好き歴史好きな方の間ではとても有名な人物です。
氏治公は何故有名なのか。それは「戦に大変弱かった」からです。
数々の戦で負け続け「戦国最弱の武将」と言われています。特筆すべきは、本拠地である小田城を9回も落とされていること。

一つの勢力の中心となる城が、こんなに何度も敵に奪われるなんて話はあまり聞いたことがありません。
9回もゲームオーバーになっているということなので、もう戦国大名なんてやめちまおうか・なんて考えてもおかしくないわけです。
しかし氏治公のすごいところはそこでめげず、その度に小田城を取り戻して城主に返り咲いていること。そのため「常陸のフェニックス」とも呼ばれています。
「常陸のフェニックス」小田氏治公のエピソード
【PR】
 ポンコツ武将列伝 [ 長谷川ヨシテル ]
ポンコツ武将列伝 [ 長谷川ヨシテル ]
氏治公の初陣の話。
一般的に初陣は「絶対勝てる!」という戦に参加することが多いようです。氏治公が父の指示で参加したのは川越城の戦い。8万の関東管領上杉軍がわずかな北条家の兵が籠る川越城を大軍で囲むという圧倒的兵力差の戦いで、氏治公は上杉方として参戦します。しかし、皆さんご存じの通りこの戦いは北条軍が奇跡的に勝利。有名な川越城の戦いのとき、敗走する上杉軍の中に・・氏治公もいたのです。はじめからついていないですね。
初陣を奇跡の敗戦で飾った氏治公ですが、その後の戦いでも負け続けます。本拠地小田城はたびたび周辺の大名たちに攻めまくられ、9回も敵に奪われたと伝わっています。小田城に攻撃をしかけてくるのは主に結城氏、多賀谷氏、佐竹氏などですが、越後の軍神上杉謙信にもしっかり攻められています。その度に氏治公は小田城を捨てて家臣の城などに逃げ込むのですが、その後不思議と小田城を取り戻すのです。

どうやって取り戻したのか興味が沸きますが、どうやら小田家には優秀な家臣がいたようで、彼らの活躍によるところが大きかったのでしょう。
まあ自分の城ですからどこから攻めたらいいかも十分わかっていたのでしょうね。
他に、ひたすら謝って上杉謙信に小田城を返してもらったこともあるようです。
ここまでは頼りない氏治公ですが、良いところもあります。それは家臣をはじめ領民たちに大変慕われていたということ。
領民たちは小田城が敵の手に奪われると年貢を納めず、わざわざどこかに逃亡している氏治公のもとに届けたそうです。これでは敵方からみれば小田城を奪っても何にもなりませんね。氏治公は戦には弱くても不思議な魅力ある人物だったのでしょうか。もしかすると城を取り戻すとき、陰で領民たちが協力したのかもしれませんね。
氏治公が心から愛した「小田城」を見学させていただく
【PR】氏治公が好きになったらこれ!
 小田氏治 (おだうじはる) オリジナル プリント Tシャツ 書道 習字 【 戦国武将 】 メンズ レディース キッズ S M L LL XL XXL 120 130 140 150 G-S G-M G-L 【 ギフトTシャツ おもしろtシャツ 記念日 誕生日 お祝い プレゼント 等 】
小田氏治 (おだうじはる) オリジナル プリント Tシャツ 書道 習字 【 戦国武将 】 メンズ レディース キッズ S M L LL XL XXL 120 130 140 150 G-S G-M G-L 【 ギフトTシャツ おもしろtシャツ 記念日 誕生日 お祝い プレゼント 等 】

茨城県つくば市。国道125号線からちょっと外れたところに小田城の跡があります。細めの道を入っていくと無料の駐車場がありますのでそこへ停めます。
小田城の本丸跡は発掘調査結果に基づいて堀と土塁が復元されています。土塁は高く堀は広く、なかなか立派な城に見えますね。「何度も落城した城とは思えないな」というのが第一印象です。
最も復元ということなので、堀の幅はともかく、当時の土塁の高さがどのくらいだったのかはまったくわかりません。

橋を渡って土塁の中に入ってみましょう。見渡す限り平らな広い空間が広がっていますね。空が青く、とてもすがすがしい景色です。北側には山が迫っており、遠くに見えるのは筑波山なのだと思います。
地面に見えるコンクリートの部分は何かの建物があった場所。氏治公が生活した御殿はこのあたりに建っていたと考えられています。この区域の周りには溝が掘られ、場所によっては土塁によって遮断されています。本丸の中はその目的によっていくつかの区画に分けられていたようです。

ちょっと離れた場所には休憩所を兼ねた建物が復元されています。
発掘調査によってこの建物は3回ほどの建て替えが行われたことがわかっているそうです。当時の柱の跡を生かして現代工法による四阿(あずまや)として建てられています。そして復元建物の前にあるのは池。ここには庭園があったと考えられています。池の周りには石を敷き詰めた州浜(すはま)があり、築山もあったと想定されます。

こんな静かな場所に設けられた庭園と御殿。氏治公はなかなか優雅な生活をしていたようですね。
そういえば小田家が行う宴会は派手でとても有名だったとのこと。「今年もやっているようだぞ」と近隣の大名にも知られていたようです。そして小田城の城兵たちが酔っ払った隙を狙って攻撃され、それで小田城は1回落城しています。何とも言えませんね。

現地にある「小田城遺構復元広場」の図を見てみましょう。ほんとここは案内看板が充実していますね。キレイでとても見やすいです。
真ん中の四角い部分がこれまで見てきた本丸です。ここに氏治公の館があり、庭園を眺めながらの優雅な生活を送っていたんですね。
りんりんロードという道がありますが、これは昔ここを走っていた鉄道の跡。当時は城の跡をまっすぐ貫いていたんですね。しかし見事な「貫きっぷり」ですね。自分の大切な城が串刺しにされてしまったことを知ったら、氏治公はどのように思ったのでしょう。
小田城の本丸は、南北145m、東西130mの四角い形をしています。これは小田城がもともとはこの大きさの「館だった」ということを示しています。
ここに初めて城が築かれたのは鎌倉時代。小田様のお屋敷という感じです。堀の水は灌漑用の用水を兼ねていて、周囲には水田などが広がっていたのでしょう。
意外とヤル?小田城の防御施設

本丸には北、東、南西の三か所に出入口が設けられていました。そしてその外は馬出や曲輪で守られています。
本丸の形をよく見てみると、奇妙に出っ張っている場所が数か所あります。これは城に攻めてくる敵兵に対し正面からだけでなく横から弓鉄砲で攻撃できるような櫓台の跡だと思われます。

本丸の南西にあった入口の外側は、四角い形の馬出が築かれていました。
門を守るだけでなく出撃の際には陣地となる場所。兵が待機できそうな広いスペースです。外側は堀で囲まれ、馬出内の土塁からは周りの様子がよく見えます。

攻撃側は一度馬出を攻略し、その後向きを変え、橋を渡って本丸に入らなければなりません。
その先には門があり、これを攻略している間に左右の土塁の上から弓鉄砲による激しい攻撃を受けそうですね。この門の周りは立派なつくりで、石垣が使われていたようです。
(現在見える石はレプリカで本物は地下に眠っているようなのですが、すごくリアルに再現されています。)

最弱の城?と思っていた小田城のイメージが変わってきました。ここで昔の小田城の図を見てみましょう(慶長年間の様子を江戸末期に書き写したもの)。
真ん中の四角い部分が本丸、外側に先ほど見てきた東曲輪や南西の馬出が見えます。
驚くのはさらにその外側にいくつもの曲輪が広がっていること。一番外側からは三重四重の堀と突破しなければ本丸に到達できないようになっています。これを見ると小田城は館づくりの小さなつくりではなくかなり大きな城だったことがわかります。
小田城の周りを歩いてみると、堀や曲輪の跡だろうと思われる地形がたくさん残っています。はじめは小さな館だったのでしょうが、のちの時代に城域がどんどん拡張されていったのでしょう。
氏治公は最弱武将だった?としても、小田城は最弱の城ではなかったのです。
それではどうして「何度も落城したのか?」を考えてみた

ここからは現地で感じた独自見解を紹介したいと思いますが、史実と異なることがありますのでご承知ください。
小田城が何度も落城した理由の一つ目は「氏治公の戦略ミス」。
ある戦いのとき少数の敵が山の上に待ち構えているのを見た家臣が「これは罠ですぞ」と氏治公に進言しました。すると氏治公は「なるほど、そうだな」と納得したような返事をするのですが、その後何も聞かなかったかのように突撃をかけてしまったという話があります。もちろん小田軍は撃破され大敗。
そんな氏治公なので、しなくてもいい戦いを何度も仕掛けて城に敵を呼び込んでしまったことがあったのかもしれません。それでも付き従ってきた小田家家臣団ってスゴイですよね。
二つ目は、「取られても取り返す作戦だった」というもの。
城を必死に守り抜けばそれだけ味方の被害も大きくなります。だったら早めに逃げて被害を小さくし、チャンスを待って城を取り戻した方がいい!と考えていたのかもしれません。何度も落城しているのに氏治公が捕まらなかったのは早めの避難が行われていたから。「あそこまで敵が迫ってきたから今回も駄目だな」なんて判断は素晴らしく早く正確に行われたのでしょう。
小田城を取り戻すにはここから攻めればいい!なんてことも氏治公以下小田家家臣団は熟知していたのかもしれませんね。
そして三つめは、これまで見てきた小田城は佐竹氏が改修したもので、氏治公の時代はもっと小さな城だったというもの。
小田城は1569年に落城した後氏治公の手から離れ、その後廃城となるまで佐竹氏の城となります。佐竹氏は小田城に手を加えたと考えられており、氏治公が楽しんでいた池の一つはこのとき埋められてしまったようです。小田城がいつ頃大きな城になったのかはわかっておらず、周りのたくさんの曲輪が佐竹氏の手によるものであれば、氏治公の小田城はすぐに落城してしまうようなほんと小さな規模だったのかもしれません。
そうであったら氏治公と小田城は戦国最弱だった・・ということになりますね。
【PR】それでは筑波山のお米でも食べましょう・・。
 ★新米★白米 15kg 恋瀬姫の舞 5kg ×3袋 令和6年産 「筑波山麓厳選 こしひかり」 送料無料 k06 茨城 お米 こめ 15キロ ブランド米 高級米 おいしい 美味しい お取り寄せ コシヒカリ ランキング 特A 1位 米 15kg
★新米★白米 15kg 恋瀬姫の舞 5kg ×3袋 令和6年産 「筑波山麓厳選 こしひかり」 送料無料 k06 茨城 お米 こめ 15キロ ブランド米 高級米 おいしい 美味しい お取り寄せ コシヒカリ ランキング 特A 1位 米 15kg