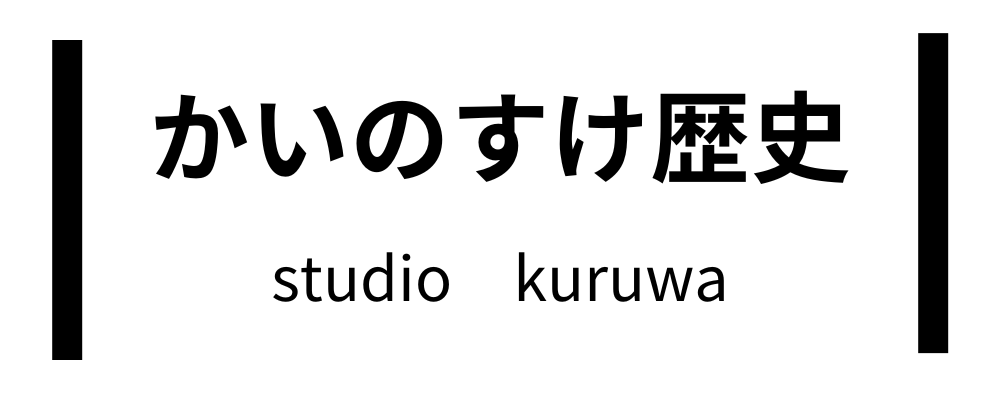首都圏から近く、人気のある小田原城。
再建された天守をはじめ、数々の門や櫓は白で統一されとても美しい。
現在城の跡は相模の自然を感じられる公園となっており、多くの観光客が訪れます。
ところでこの美しい小田原城。戦国時代は日本でいちばん大きく最強の城であったことはご存じですか?
小田原城は戦国大名北条氏の本拠地。
北条氏は関東のほとんどを支配下に置く東国一の勢力を誇り、約100年にわたってこの地を治めていました。
ところが豊臣秀吉の天下統一の最後の戦いとなった「小田原征伐」(1590年)で、城は包囲され北条氏は降伏することになります。
この戦いでの小田原城籠城戦は約3カ月という長期間にわたって行われ、その間豊臣軍は城の中に一歩も入ることはできませんでした。
豊臣軍の兵力はおよそ20万。対し小田原城内の北条軍の兵力は多く見積もっても5万程度。大きな兵力差がありながら小田原城が力攻めで落城しなかった理由は一体何だったのでしょうか。
実は、その理由を示す痕跡が、小田原城の周りにいくつも残っているらしいのです。
今回は、小田原城の周りに点在する「惣構」の跡を巡り、本当に「最強の城」だったのか考えてみます。
「惣構」(総構)とは?総延長9キロの土塁と堀が城と城下町を囲む

戦国時代、日本で最も守りの固い城だったと言われる小田原城。その強さの理由が「惣構」です。
惣構とは城だけでなく城下町まですっぽり囲んだ防御施設。
中国やヨーロッパで見られるような城壁で囲まれた都市の「日本戦国版」です。
戦国時代の城というと、城主が政務を行い兵士が守る一般的に「城」と言われる部分があり、その外に領民が住む城下町(集落)が広がっていました。
ところが、小田原城は中心となる「城」だけでなく、城下町や田畑もひっくるめた外側に土塁や堀を備えていました。これが「惣構(総構)」です。
城と城下町を囲む防衛ラインは土塁や堀で構成され、入口には門や木戸を設置します。城だけでなく町全体を防衛することができ、ひとたび籠城戦となった場合は大軍を収容できる機能も有していました。
小田原城の惣構は長さ9キロという大規模なもの。これほどの大きさで城と城下町を防御する施設を備えた城は小田原城しかなく、これが「戦国最強の城」と呼ばれる理由となっているのです。
なぜ北条氏は巨大惣構を築いたのか
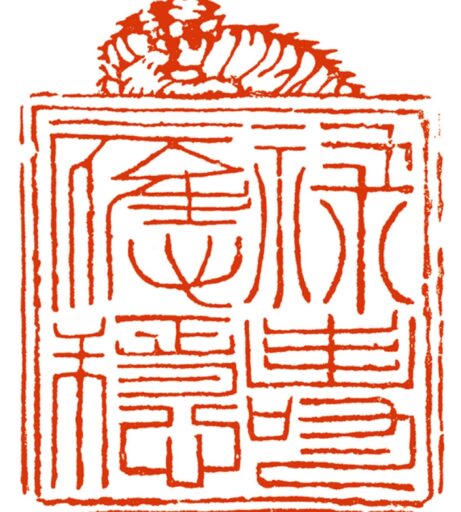
戦国時代の小田原城を支配していたのは北条氏。「関八州」とよばれた現在の関東平野の大部分を支配する東国最大の戦国大名です。
北条氏のはじまりは伊勢新九郎盛時。盛時は室町幕府に仕えていたと武将だった言われ、妹(姉とも)が駿河の今川家に嫁いでいた縁で東国に移り住み、やがて今川の武将として活躍します。
その後、盛時は独自に勢力を拡げることとなり、のちに早雲庵宗瑞と改名。伊豆韮山城を拠点に関東に勢力を拡げていきます。
二代氏綱は小田原を本拠とし相模・武蔵へ勢力を拡大。
三代氏康は関東管領上杉氏などとの戦いを制し、広大な土地を支配するようになります。
四代氏政、五代氏直の頃には東国では並ぶ者がないほどの大大名に。
本拠小田原は関東の中心都市として繁栄します。
しかし後に畿内から西日本のほとんどを統一した豊臣秀吉と敵対。
天正18年(1590年)に豊臣の大軍を小田原で迎え撃つことになります。
小田原城惣構は豊臣との決戦が現実的になった頃に普請されたものと考えられています。
小田原城はそれまでに上杉謙信・武田信玄の攻撃を防いだ名城として十分な防御力を誇っていたのですが、天下人秀吉率いる豊臣軍の来襲に備え、さらなる大規模改修が行われたのです。
「小田原城」と「惣構」が理解できる地形の話

小田原城は箱根外輪山から伸びる尾根上に築かれています。
この尾根の特徴は小田原城の近くで3つに分かれること。何だか鳥(アヒル?)の手のようです。
それぞれ北から谷津(山)丘陵、八幡山丘陵、天神山丘陵と呼ばれ、小田原城は真ん中の丘陵の先端にあります。「尾根の先端に城を築く」というのは北条の得意技。初代早雲が初めて城主になった(と言われている)駿河興国寺城も尾根の先端を利用した城なので、伝統芸とも言えるかもしれません。
(実際のところは北条だけでなく、戦国時代多くの城が台地や尾根の先端に築かれていました。この地域の地形の特徴なのかもしれません。小田原城は北条氏が入る前に大森氏の城であり、昔から使われていました。ただ、このような地形を城郭化するノウハウを北条氏が持っていたと考えられます。)
小田原城は東から南を山王川と海、早川で守られた位置にあります。北と西は山となっているのですが・・唯一守りの弱い場所があります。
それは西。
箱根山から続く尾根が小田原城までのびており、こちらから攻め込まれると防ぎようがありません。
特に3つの尾根が集まる小峯山付近の防御が課題となります。そのために必要となったのが「尾根を断ち切る工夫」でした。

北条氏は山中に巨大な堀切を築き、西側からの敵の侵入を断ち切ります。これが小峯山に残る三本の巨大堀切です(小峯御鐘台大堀切)。
更にその西側にも曲輪を設けます(水之尾口)。これは小峰山堀切の西側にまだまた高い尾根が続いていたためと考えられます。
現在でも水之尾口付近の道路を歩くと、その先でグッと下り坂になるのがわかります。巨大堀切の外部分であってもある程度の高さのある場所までは、惣構の一部としての整備がされていたようです。

残るはそれぞれの尾根に防御施設を設けること。
山から平地に至るまで堀と土塁を築き、小田原城と城下町を囲む総延長9キロにもなる巨大な惣構が出現することになるのです。
惣構はどのような姿をしていたのか

戦国時代の小田原城がどのような姿だったのか、それを伝える建築物は残念ながら残っていません。
そして小田原城の外側に築かれた「惣構」の様子も想像するしかありません。
ですが同時代に北条氏が築いた城の様子を示す遺構や資料はいくつか残され、それを基に想像することはできそうです。
小田原城は北条家の本拠。各支城で使われていたような防御施設は間違いないなく使われていたのでしょう。
惣構は敵の侵入を防ぐ施設。
万里の長城とまではいいませんが、およそ川の堤防のようなかたちのものが長くずっと続いている様子を想像してもらうと良いと思います。
小田原城の惣構は堀、土塁、そして櫓や塀などで構成されていました。
それらのパーツがどのような姿をしていたのか、関東各地の北条家の城跡の様子をザックリ紹介します。

まずは堀。
惣構のほとんどは曲輪(この場合は小田原城内全てをいうことになるのでしょうか)に対し、横向きに堀が設けられていた(横堀)と考えられます。
高台である山の部分は空堀で、堀底には敵兵の移動を阻む目的で畝が造られました。
現在、山中城や河村城に見られるような畝堀となっていたのでしょう。

次は土塁。
小田原城惣構の土塁の傾斜角度はおよそ50度。現在はだいぶゆるくなっていますが、当時はまるで壁のような姿をしていました。
その様子は北条氏邦の居城、鉢形城の土塁のイメージが合うと思います。
画像では芝が貼ってありますが、戦国時代は土がむき出しの状態。しかも関東ローム層という赤土でできており、ツルツルした手も足もかけられない絶対に登ることができない防御施設でした。

最後は櫓(矢倉)と塀。
惣構のうち、重要とされる場所には櫓や塀が建てられていたと考えらえます。その姿はあくまでも東国の戦国スタイル。逆井城に再建された井楼矢倉のような建物だったのだと思われます。
小田原城「惣構」の痕跡を巡る
戦国小田原城の「惣構」の痕跡は現在でも見ることができます。
周囲9キロにわたる日本一の城の防御施設の跡を見ていきましょう。

その前に、ふたつ確認しておきます。
ひとつは、戦国時代の小田原城の中心となっていた場所は、現在天守のある本丸ではないこと。
戦国時代の小田原城の本丸は、もう少し山側にあったようなのです。
それがわかる場所が八幡山古郭(はちまんやまこかく)。小田原城天守からJR東海道線を挟んだ北側にある丘です。
標高69m程のこの場所に戦国時代の小田原城の遺構が集中しており、北条氏時代の本丸だったのでは・・と考えられています。
現在の小田原城で考えると「惣構ってずいぶん山側に寄っているな・・」と感じますが、八幡山古郭を真ん中に考えればスッキリします。
ふたつめは、惣構遺構には「山部分」と「平地部分」があること。
小田原城と城下町の周りをすっぽり囲むには、山にも平地にも惣構を築かなければなりませんでした。
ということで見学ルートは起伏が激しいです。
そして「平地部分」の遺構は市街化が進み、こじんまりとしています。
一方「山部分」の遺構は残り具合がよく、間違いなく感じるものが違います。
はじめに「平地部分」をサッとみていきましょう。
① 早川口遺構(はやかわぐちいこう)

早川口は小田原城の西側の入口。現在の道路でいうと、小田原市内を走る国道1号線から熱海方面に向かう国道135号線に分岐したすぐ先にあります。
遺構は住宅街の中にあり、駐車場もありません。
北条氏時代には虎口があったと考えられている場所で、二重外張(ふたえとばり)という土塁と堀を二重に配した造りになっていました。
低地に残る貴重な遺構なのですが、土塁とわかる部分と隣の低地(堀か?)、そして住宅の立つ一段高い場所が並ぶという「ちょっと想像しにくい」様子となっています。
土塁の断面を発掘調査したところ玉石が2m以上にわって積み上げて築かれていることがわかり、手の込んだ造りであったようです。
② 江戸口見付

小田原城下町の東の入口である江戸口見付。
惣構の東端は山王川で、東から川を渡ったすぐの場所に小田原の入口がありました。
江戸時代には城下を警護する重要な地点としての役割があり、土塁によって右左と屈折する形となっていました。また江戸日本橋からちょうど20里の位置にありそれを示す一里塚が設けられていました。
現在は国道一号線の脇に松(当時のものであるか不明)があるだけで、遺構は残っていません。ちょうど歩道橋があるので、「ここから先が小田原城下だな」って思える場所であります。
③ 蓮上院土塁(れんじょういんどるい)

江戸口見付のすぐ近くにある土塁跡。
ここも住宅街の奥にあり、道は行き止まりになります。
また土塁は金網に囲まれているため外から眺めるだけ。想像力が大切な場所です。
当時はこの土塁の東側に水堀があったとのこと。
現在その様子を伺うことはできませんが、かなり広い堀だったようです。
小田原征伐の際には、ここの水堀を挟んだ反対側に徳川家康が布陣していました。
土塁の一部が無くなっているのは太平洋戦争中に爆弾が落ちたためといわれています。
④ 城下張出(しろしたはりだし)
ここからは見どころの多い「山部分」
小田原駅西口の先、県道74号線「小田原税務署西」(ファミリーマートのある交差点)を入ったところにある惣構遺構です。

キツイ坂道を登った先の住宅街の中に、巨大な土塁が姿を見せます。
NHK「ブラタモリ」でタモリさんが登ろうと「チャレンジした」土塁です。

実は坂道をもう少し登っていくと上から見ることができます。
ここは惣構のラインから凸状に張り出した部分。
上の画像(写真)でいうと、左側(北)に向かって出っ張った形をしています。
惣構にとりつく敵兵に対し側面攻撃(横矢)ができるようにした工夫です。また北側への出入り口であった可能性が高いと言われています。
上部見学場所である「平場」から北側を見ると、民家の二階と同じ目線でちょっと気が引けます。あまりガヤガヤしないでスッと見学を済ませたい場所です。
ここは谷津山丘陵になるのですが、下との高低差がかなりあるのがわかります。
別の場所になりますが、丘陵に登る坂道はとても急でグッと曲がっていますね。
城下張出もそうですが、この後に紹介する惣構の「山の部分」はすべて高い場所に設けられていることがポイントです。
⑤ 山ノ神堀切

城下張出から南西に。この道は、小田原城の一番北を守る八津山丘陵(やつやま)の上を走っています。
右側に見えてくるのが山ノ神堀切。尾根をぶった切る防御施設です。
発掘調査は今のところ行われていないということですが、おそらく当時はもっと深くとがった堀で断ち切られていたのだと思われます。

山ノ神堀切の奥に進んでいくと惣構の堀と土塁が見えます。
江戸時代にはここに門が設置され、「山番」と呼ばれた小田原藩士によって門が開閉されていたようです。
堀の向こう側(右手)に土塁のようなものがありますね。これは「掻き上げ土塁」でしょうか。次に紹介する「稲荷森」と同じ造りになっています。
⑥ 稲荷森

山ノ神堀切からもう少し西に進んだ場所。
車がすれ違えないような狭い道路の脇にある看板を入ったところにある遺構です。
行き止まりの先にこのような景色が広がり、思わず声が出てしまいそうな感動スポット。
堀がちょうど曲がっている位置にあります。
竹藪の部分は「掻き上げ土塁」となっていたよう。空堀の外側にも土塁があり、攻め手から見ると直前まで空堀の存在に気づかない怖い仕掛けです。
これは山之神堀切の外側でも見られました。
稲荷森はここの字名。竹林の景観と相まって、やたら雰囲気の良い場所です。
⑦ 小峯御鐘ノ台大堀切

小田原城惣構最大の見どころです。
はじめに紹介しましたが、小田原城防御の要となる場所。
箱根山から小田原城に続く尾根上に位置する、小田原城の弱点でした。
ここから敵兵の侵入を許したら小田原城は終わり・・。
そのため古くから「東堀」が設けられていたと考えられています。
さらに天正18年(1590年)の豊臣軍との戦いを前に「中堀」と「西堀」が追加。
三重の堀切で防御する作戦ですね。
それぞれの堀切の規模は全国最大級。攻めかかる豊臣軍にとっては迷惑この上ない防御施設です。
城内側から順に紹介します。
東堀切

本来は三の丸新堀の一部でしたが天正15年(1587年)から中堀・西堀が構築され、三連堀切の一番城内側の役割を担うことになりました。
掘の幅は25~30m、発掘調査結果による深さは12~15mもあったということ。現在の深さは10m程なので、当時は5m以上も深かったことになります。
堀法面の角度はおよそ50度~60度。とても人が登れる傾斜ではありません。
堀底は畝によって区画された障子堀であったことが確認されています。
現在の堀の長さは約280m。途中で2箇所屈折している部分があり、「横矢」を仕掛ける工夫があったことがわかります。
中堀切

東堀のすぐ隣にある堀切。
現在は道路になっており、舗装されていませんが車が通ることができます。
山ノ神堀切、稲荷森から続く道路はこの中堀に通じています。
道路は途中で屈折しており、東堀と同じように「横矢」をねらった造りとなっています。


面白いのは東堀との距離の近さがわかること。
中堀の柵がある場所に不思議と切れ目があり、そこから東堀が見えるのです。
上の2枚の画像は中堀のほぼ同じ場所から撮影したもの。右画像の道路部分が中堀。柵を挟んで左画像奥に見えるのが東堀。
その距離は数10m程しかなく、中堀が東堀のすぐ隣に設けられたことがわかります。
西堀切

中堀切の上の坂道を登ったところにあります。
説明看板の右奥にも掘の遺構があり、途中まで埋められた?状態となっているようです。
右手の通路を進むと堀底におりることができ、最終的に崖のような地形にあたります。
3つの堀切のうち一番外側に位置し、西側から敵兵が侵入してきた場合最初に交戦する場所ということですね。
西堀の外側が高くなっているのが気になります。
その先は次で紹介する水之尾口で防ぐ構造になっていたようです。
⑧ 水之尾口(櫓台)

個人的にいちばん興味のあった場所。
小田原城の絵図を見ると西側に突出しており、「ここはいったいどのようになっていたのだろう」と思っていたのです。
小峰の大堀切の外にあり、まるで出丸のようにも見えますね。
水之尾口は、標高約120m、惣構の一番西に位置し、箱根山から続く尾根沿いに侵攻してきた敵兵をいちばん初めに迎撃する地点でした。
現地に行くと狭い道路の隣に畑が並ぶ細長い尾根であることがわかります。
北側(北東)の眺望は良く、遠く相模湾を望むことができます。西側は林があって何も見えません。

櫓台があったと言われる場所は畑となっており、遺構があるのかどうかもわかりません。
ただ、現地を訪れるとすごくわかることがあります。
それはなぜこの場所が惣構の先端になっているか。
注目したいのは道路。
この先はグッと下り坂になっています。
足を進めてみると下り坂の勾配はどんどんきつくなり、森を抜けた地点ではかなり低くなっていることがわかります。
ということは、水之尾櫓台が周辺でいちばん高い位置にあるのですね。
箱根山から続く尾根上にあり小田原城最大の弱点であるのですが、その一番高い場所ギリギリまで含めて惣構としているところがさすがです。
小田原城惣構を超えることができなかった豊臣軍
これまで紹介してきた小田原城の惣構。
ほかにも市内各所に遺構があり、戦国時代の小田原城が「最強」だったのは本当のようです。
豊臣秀吉との戦いで惣構はどのような働きをしたのでしょうか。
簡単に紹介します。
小田原城の押し寄せた豊臣軍は20万を超える大軍。
現地案内看板によると秀吉は陸だけでなく海にも水軍を配しており、小田原城内に籠城した5万人の北条軍は総構の内部から一歩も出ることができない状態になりました。
しかし戦いはここから進まず、最終的に豊臣軍は小田原城惣構を打ち破ることはできませんでした。
秀吉が力攻めを避けたという可能性もありますが、その判断の一因に総構の存在があったことは間違いありません。小田原城を囲む巨大な堀と土塁は鉄壁の防御力を見せつけたのです。
小田原城に籠る北条家当主氏直は約3ヶ月籠城した後豊臣秀吉に降伏。小田原城は開城し、北条家はここに滅亡します。
戦後、畿内に戻った秀吉は小田原城をヒントに、京都(御土居)や大坂城に惣構を築きました。
他の大名たちも秀吉にならって自身の城に惣構を設けることに。
こうして、小田原城の惣構は全国の城造りに大きな影響を与えることになったのです。
ご注意
今回訪問した遺構のほとんどは住宅街や山間部にあります。
現地の道路はとても狭く、また駐車場もありません。
見学の際は徒歩、または自転車・小型バイクなどをおススメします。